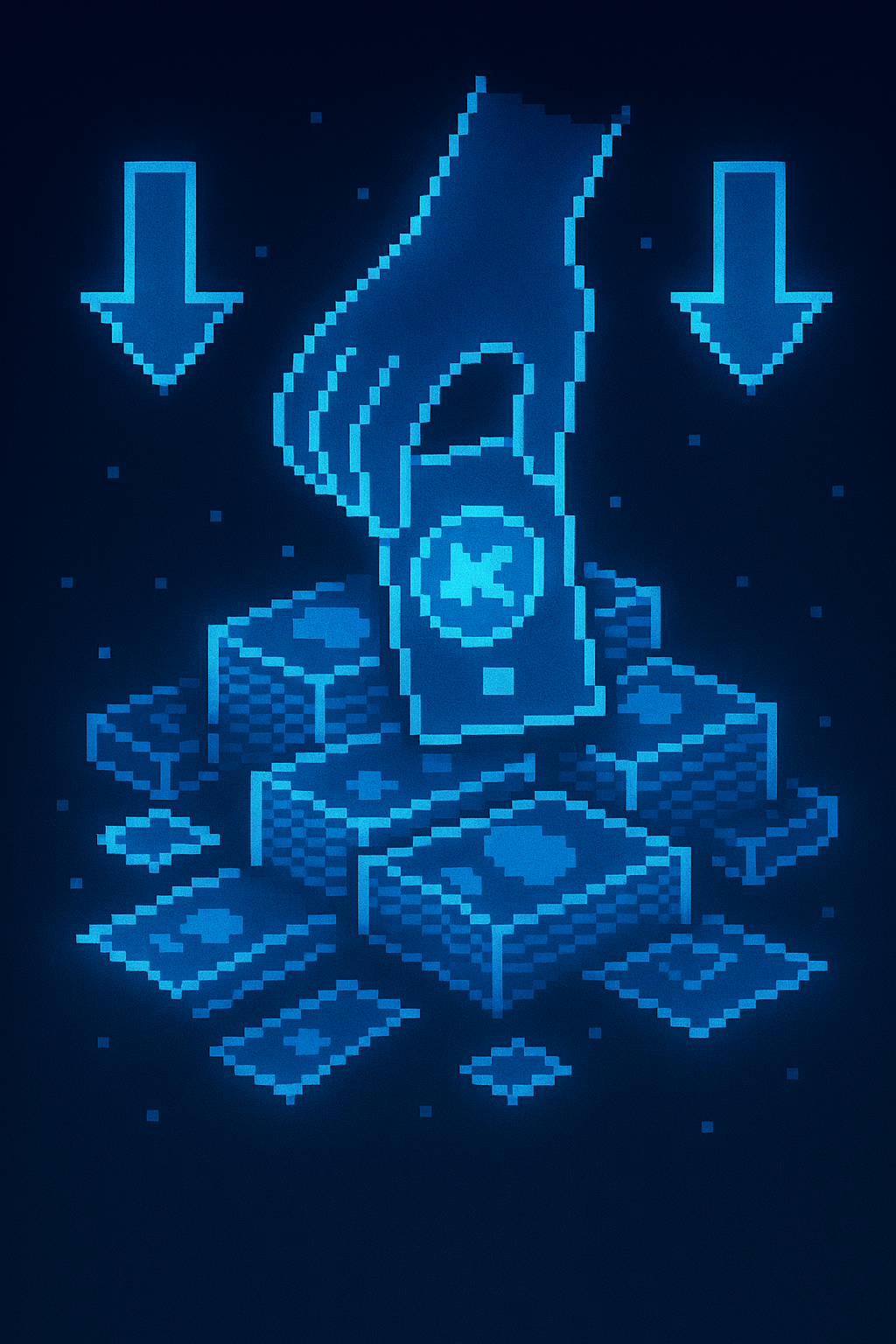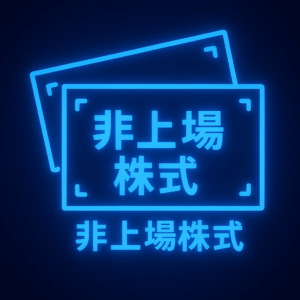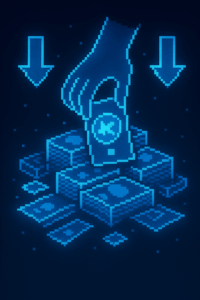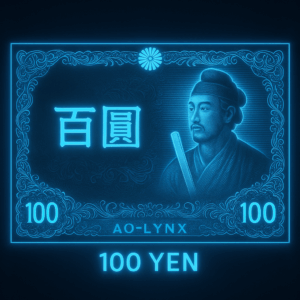①国内債務調整の歴史
・かつて日本は第二次世界大戦後、預金封鎖、デノミネーション、財産税、戦時補償債務の同額課税相殺による、戦時中の債務の全額踏み倒しを行った。
②時系列:敗戦によるハイパーインフレ
(1)1946年2月17日
〇日本銀行券預入令
・国民の財産はすべて銀行に預金することを強制し、タンス預金などを禁止しました。
・目的→国民の財産、資産額の把握のため。
〇金融緊急措置令公布
・いわゆる「新円切替」です。国民の手元にある旧円は使えなくなりました。
・目的→日本銀行券預入令と同日に同法を施行することで、国民の財産・資産を政府が差押するため。
〇臨時財産調査令公布
・日本銀行券預入令、金融緊急措置令により、差押した資産を調査することとしました。
※上記の3法令は、前日16日の夕方に渋沢蔵相によるラジオ演説を通じて行われ、わずか1日で実施されました。こうした措置について、当時政府は「インフレ抑制のため」と国民に説明しました。
(2)1946年7月24日
〇戦時補償全面打ち切り閣議決定
・表記の通り国民向けの戦時補償の全面打ち切りを行いました。
(3)1946年10月19日
〇戦時補償特別措置法
・政府が負っている、国民の戦時補償と同じ金額の戦時補償特別措置税を課税しました。
・目的→政府の国民に対しての補償を踏み倒すため。
(4)1946年11月12日
〇財産税法公布
・ついには封鎖した預金に対して課税を行い、国民の財産権を侵害し、財産を政府が強制没収しました。
※本記事は投資助言ではありません。