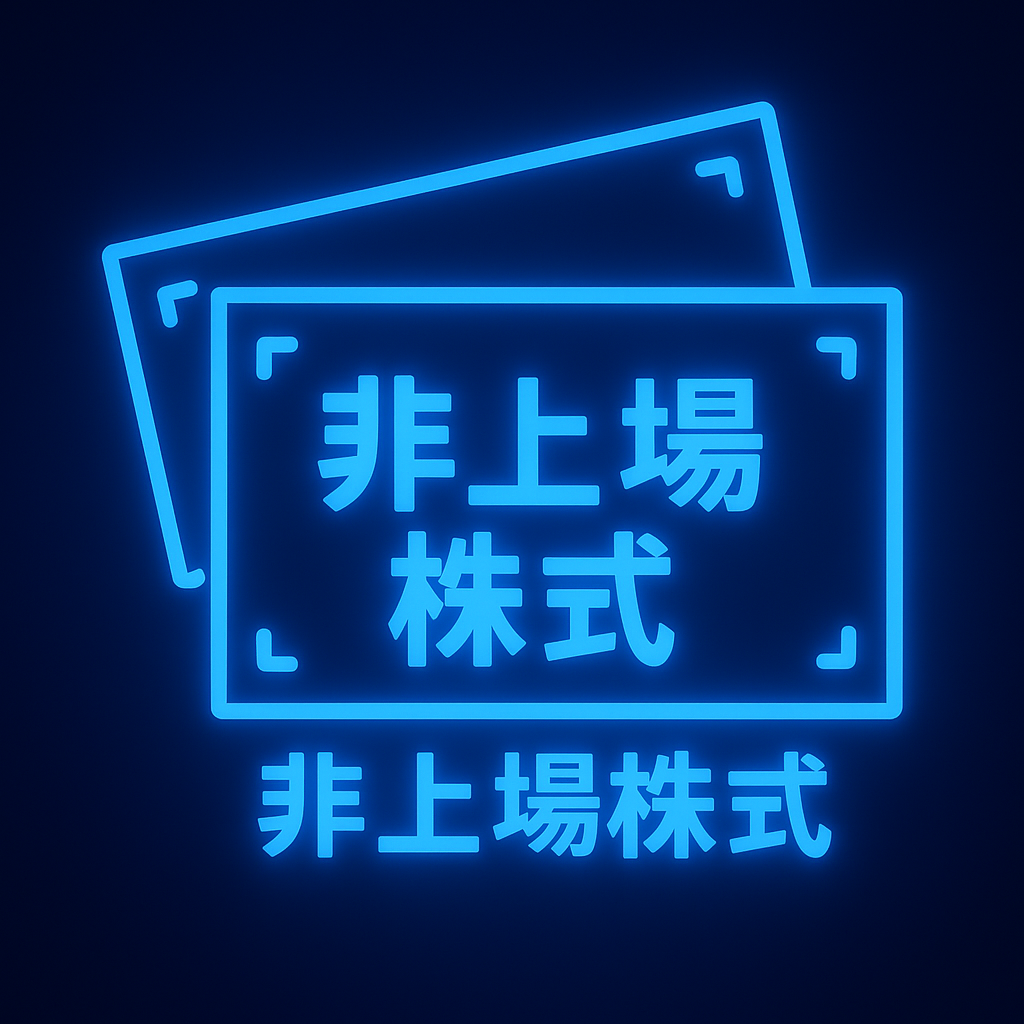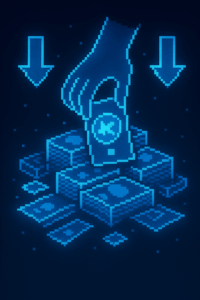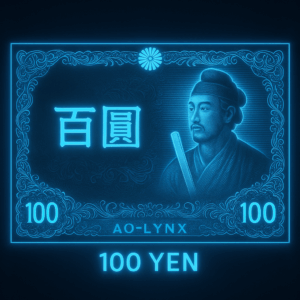1.トップ面談
・M&Aを行う企業の経営者同士がM&Aの面談を行います。
2.意向表明書(Letter of Intent)の送付
・買い手側が交渉前に希望を伝えるために作成します。法的拘束力はありません。
3.基本合意書(Memorandum Of Understanding)の締結
・買い手側が交渉を実施した後に合意形成を図るため、作成します。一部法的拘束力があります。
・上記ののちにデューデリジェンスを行います。
→①事業DD:どのような事業なのか、集客はどのように行っているか、売上はどのように発生するか、社内の営業から売上発生までのオペレーションなど、事業活動がどのように行われているのか、を審査します。
→②財務DD:決算書、ならびに会計ソフトの仕訳を一件ずつ公認会計士が確認し、会計処理が適切かの審査を行います。審査後、不明点について、買い手の財務担当と公認会計士からのインタビューが行われます。
→③法務DD:法律に基づいて事業が行われているか、許認可については適切に取得し運用がされているか、取引先との契約書は締結されているか、またその契約書の内容に問題や不備がないか、を審査します。買い手の法務担当と弁護士からのインタビューが行われます。
→④税務DD:税務申告、納税が適切に行われているか、決算書ならびに会計ソフトを確認し、審査します。後日、買い手の財務担当と税理士からのインタビューが行われます。
→⑤労務DD:従業員との雇用契約が適切に行われているか、残業代未払いが無いか、残業計算は正しいかを賃金台帳、懲戒解雇を行ったことがあるか、過去パワーハラスメントなどの発生の有無を雇用契約書、出勤簿などを基に審査をします。後日、買い手の法務担当と弁護士からのインタビューが行われます。
などがあります。
上記によって生じた損害は株式の譲渡後も、譲渡人が補填するよう、補足がつくことがあります。
例)従業員からの、残業代未払い請求があった場合に、旧株主がそれを補償する。
4.最終契約書(Definitive Agreement)
・最終契約書は正式なM&Aの契約書のことです。M&Aのスキームによって実際の名称は異なります。株式譲渡の場合には株式譲渡契約書(Stock Purchase Agreement)となります。
・買い手側がM&Aの最終合意を図るために、デューデリジェンス実施後、作成します。法的拘束力があります。
5.非上場株式譲渡の決済当日の流れ
主に相対取引で行われます。譲渡制限が定款に定めてある場合には、対象企業からの譲渡承認を得る必要があります。
①譲渡制限株式を譲渡する場合、下記が必要です。※定款に記載あり。
(1)株式譲渡承認請求書
・株式の譲渡者は株式譲渡承認請求書に譲渡する株式の種類および株式数と株式を譲渡する相手の氏名または名称を記載し、承認手続きをします。
(2)株主総会議事録
・上記請求に対して株主総会を行い株主総会議事録を作成します。
(3)株式譲渡承認(不承認)通知書の作成
・株主総会が実施されたら、株主総会の決議の内容を株式譲渡承認請求を行った譲受人に通知しなければなりません。
→ご参考:株式譲渡承認請求書、株式譲渡承認通知書、株主総会議事録
(4)株主名義書換請求書
・株式の譲受の契約が成立したら、実際に株式を発行している会社であれば、株式の名義を書き換える必要があります。
②株主名簿の書換
→ご参考:株主名義書換請求書
→ご参考:株主名簿記載事項証明書交付請求書で株主名簿記載事項証明書を請求可能。
③取締役の決定書
→株主に通知に通知。
④取締役登記の変更
・司法書士が決済当日に行います。
・社判、実印、印鑑証明カードの受け渡し
⑤売買代金の支払
・譲渡人から譲受人にSPA記載の方法を用いて、売買代金を支払します。
・譲渡金の支払方法や期限はSPAに記載します。