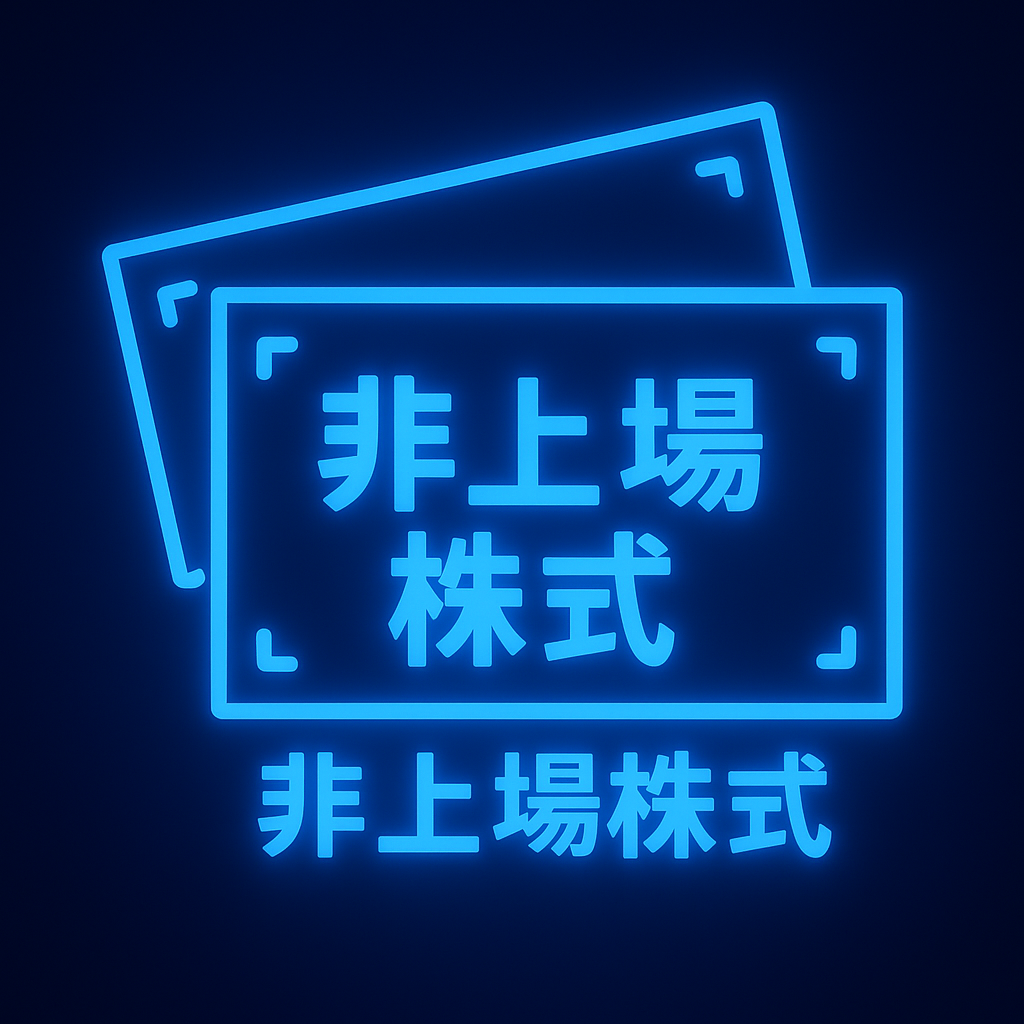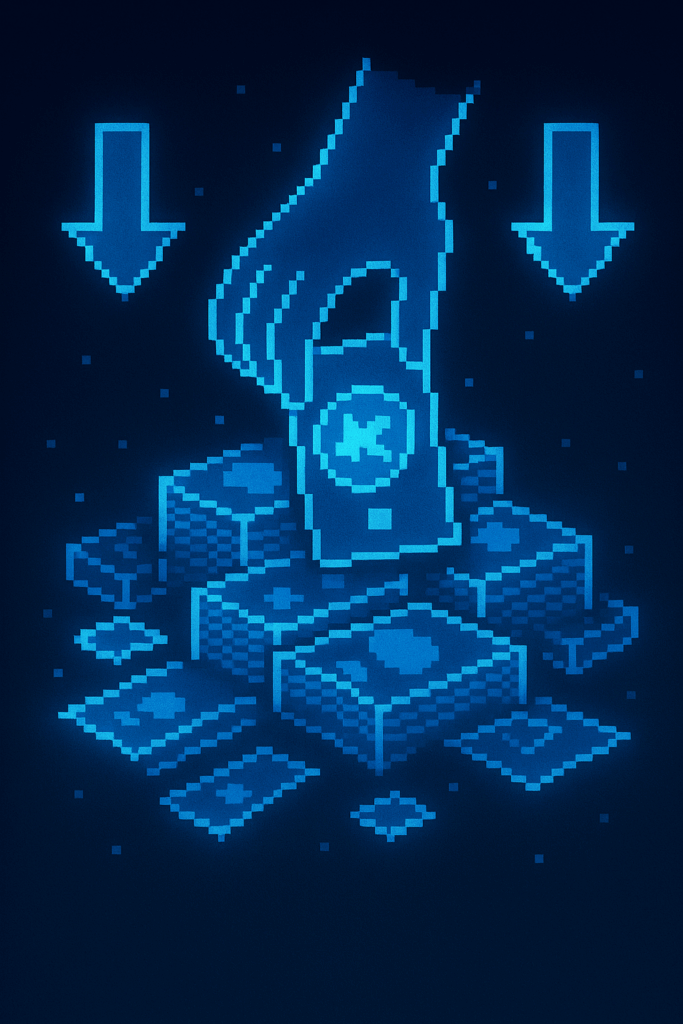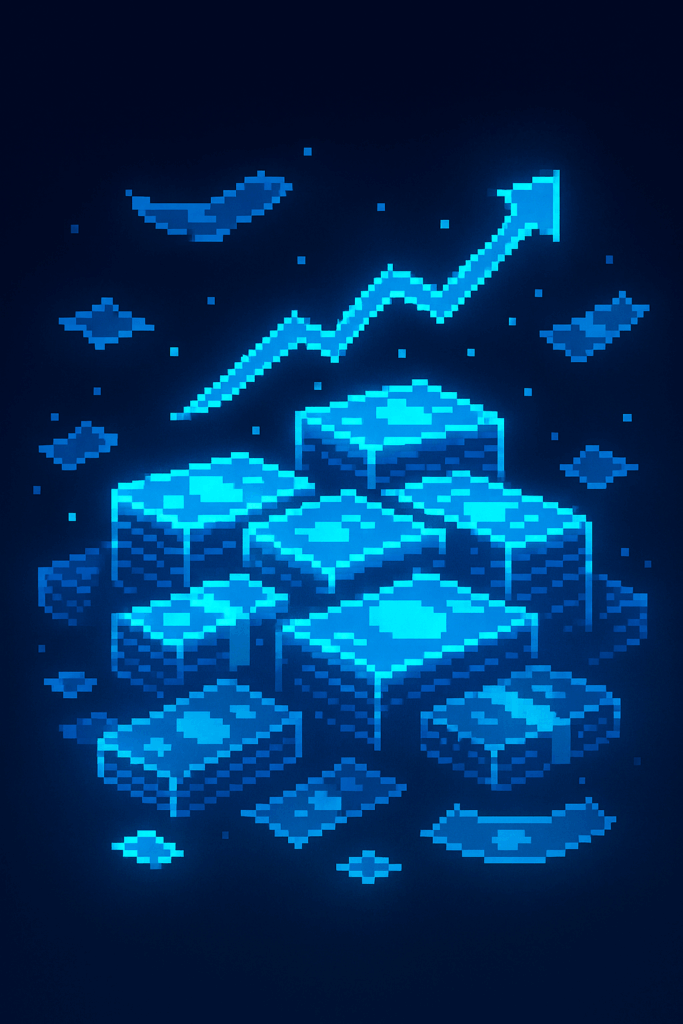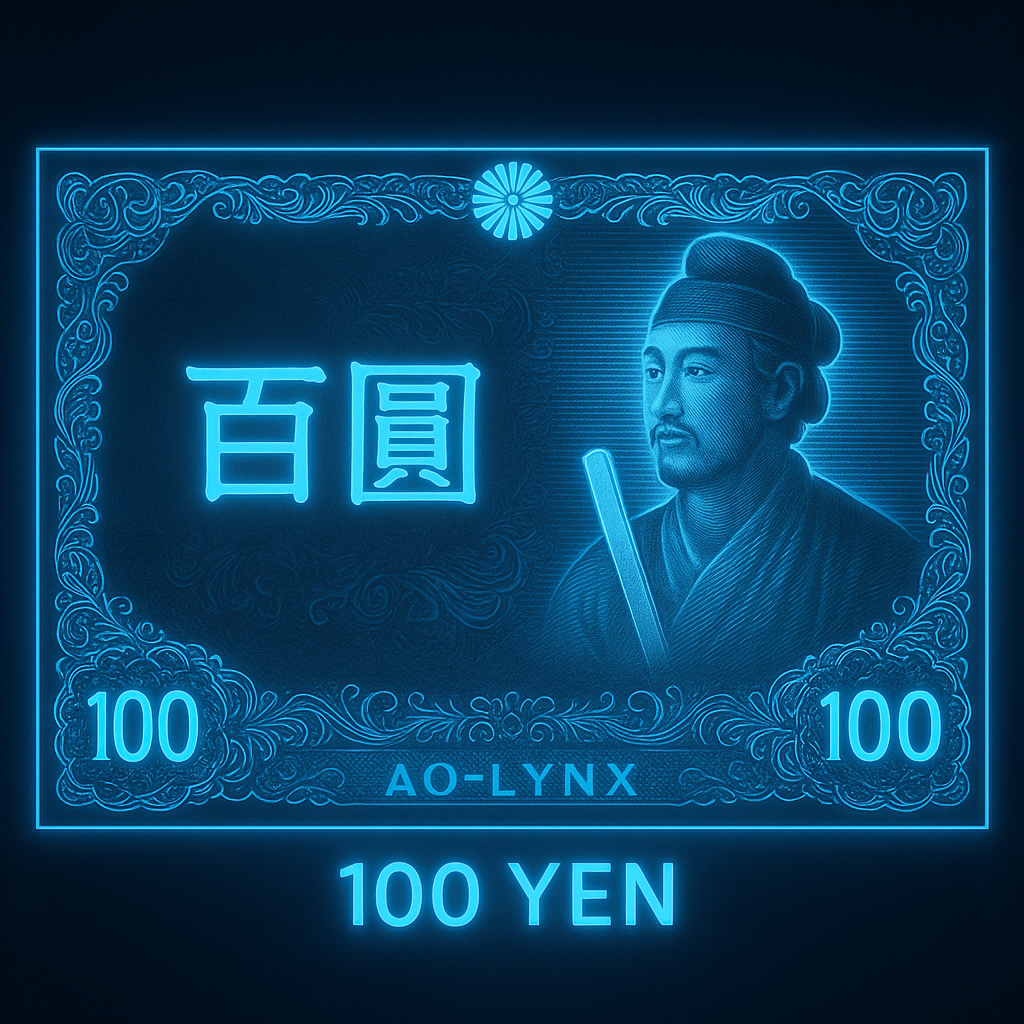金融– category –
-

1946年 新円切替当時の資産防衛
● ● (1)株式市場を利用した防衛 1.預金封鎖直前で預金を引き出しした事例 ①別記事で触れましたが、当時は紙媒体での新円の発行が間に合わず、暫定的に旧円に証紙を貼付し新円の代替としました。のちに使用期限が定められ、最終的には新円紙幣に完全移行... -

東京23区・香港・シンガポールの比較について
①都市構造・行政区分 観点東京23区シンガポール香港地域区分東京都の特別区(市と同等)一国家・一都市中国の特別行政区行政構造23の自治体(区)で構成統一された国家18の区に分かれる面積約627 km²約734 km²約1,106 km²(都市部は狭い) ②人口・人口密度... -

銀行で使う漢数字の記載について
銀行では、契約書、為替手形、約束手形などで大字(だいじ)という漢数字を利用します。 理由としては、改ざんをしにくいからです。 銀行で最もよく使われる大字一覧 算用数字漢数字1壱2弐3参4四5五、伍6六7七8八9九10拾100百、佰1,000千、仟10,000萬 上記... -

M&Aの流れと非上場株式の譲渡手続きについて
1.トップ面談 ・M&Aを行う企業の経営者同士がM&Aの面談を行います。 2.意向表明書(Letter of Intent)の送付 ・買い手側が交渉前に希望を伝えるために作成します。法的拘束力はありません。 3.基本合意書(Memorandum Of Understanding)の締結 ... -

中国本土(中国オンショア)アプリのダウンロードについて
(1).金盾と中国本土のインターネット(中国本土オンショアインターネット)について ①中国には金盾(グレートファイアーウォール)というインターネット検閲があるため、日本から直接中国本土のiphoneアプリ(中国本土オンショアアプリ)のダウンロード... -

戦後日本の資産没収のまとめ
①国内債務調整の歴史 ・かつて日本は第二次世界大戦後、預金封鎖、デノミネーション、財産税、戦時補償債務の同額課税相殺による、戦時中の債務の全額踏み倒しを行った。 ②時系列:敗戦によるハイパーインフレ (1)1946年2月17日 〇日本銀行券預入令 ... -

【テーマ:近現代の徳政令③】財産税・強制徴税による強制資産没収
(1)1946年2月17日 財産税 ・戦後のハイパーインフレ抑制のための預金封鎖とともに、財産税による国民の資産を強制没収しました。 ・当時の税率は、累進税率で20万–30万円:55%、30–50万円:60%、…1500万円超で90%課税となった。 ・新円切替(デノミ... -

【テーマ:近現代の徳政令②】ハイパーインフレ・通貨危機
(1)日本の戦後ハイパーインフレと通貨危機の概要 ①戦後のハイパーインフレ ・1945年から1951年の6年で企業物価指数は約100倍も上昇しました。 ・戦後のインフレの原因は、敗戦による生産設備の破壊や軍需工場の閉鎖など、生産が無い状態である者の貨幣... -

【テーマ:近現代の徳政令①】デノミネーション・預金封鎖
(1)新円切替と預金封鎖の概要 ①1946年2月17日 新円切替: ・金融緊急措置令および日本銀行券預入令 により預金封鎖を行い、従来の円(旧円)は強制的に銀行へ預金させた。 ・1946年3月3日付で旧円のうち5円以上の紙幣の流通を差し止め、一世帯月の引... -

貴金属が返礼品のふるさと納税の返礼率比較
別記事でゴールド(金)が返礼品の自治体を紹介しました。 そのほかにもございましたので比較をさせていただきます。 ①令和7年6月4日現在の貴金属相場 (1)ゴールド(金)1グラム=約17,000円 (2)プラチナ(白金)1グラム=約5,400円 (3)シル...
12